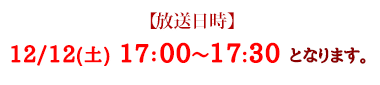大正11年、宮崎県延岡駅から高千穂を経て熊本県の高森線に至る九州中部を東西に結ぶ横断鉄道計画としてスタートした高千穂線。だがその道のりは平坦ではなかった。熊本から高森までは戦前に開通済み。高千穂から高森までが繋がれば、九州中部横断鉄道は完成するはずだった。しかし思わぬトラブルにより工事は中断。予定より短い延岡~高千穂間の路線として開業した。
国鉄民営化後は第三セクターとして営業を始めた高千穂線。「神話の里」としても知られる高千穂を結び、日本一高い鉄道橋である「高千穂橋梁」や、減少していた利用客数を増加に転じさせた「トロッコ神楽号」など、風光明媚な地に確かな存在感を持って存続していた。
ところが、決定的な災難が高千穂線を襲い、平成20年には全線が廃止となってしまった。しかしその後、地元住民が中心となり高千穂線の復興を目指していくのである。